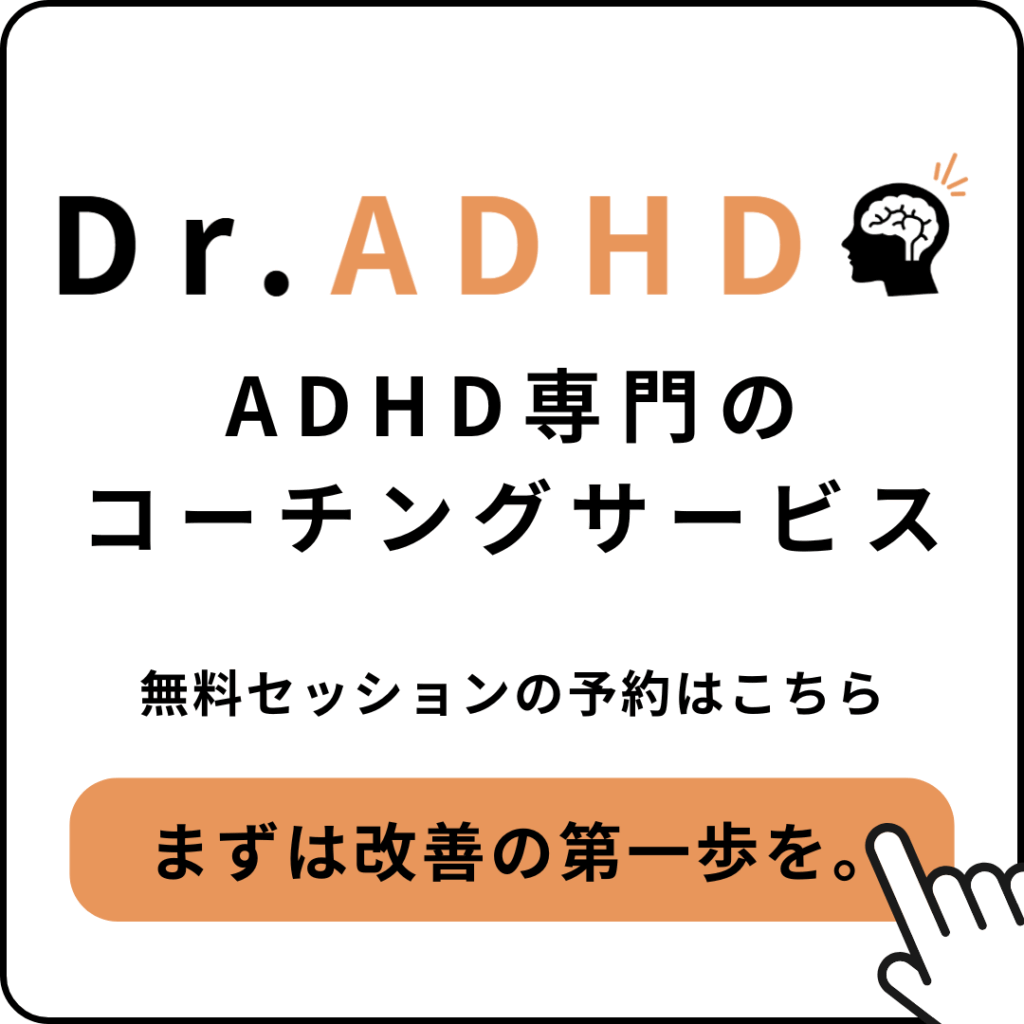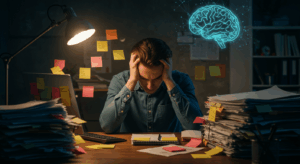【実話ストーリー】「また仕事が続かない…」転職を7回繰り返したSさんが気づいた“本当の原因”
今回はそんなタイトルで記事を書かせていただきました。
「今度こそ頑張る」そう思って転職したのに
Sさん(30代・女性)は、大学卒業後に営業職として就職。
明るく社交的で第一印象も良く、採用担当者からの評価は常に高め。
けれど、最長でも勤続1年半──それが、彼女のキャリアの“限界”だった。
最初の職場では、報連相がうまくできずに「何考えてるかわからない」と言われ、
2社目では日報を出し忘れて上司に呼び出されることが続いた。
「普通、言われなくてもわかるよね?」「空気読んでよ」そんな言葉がトラウマのように残っている。
「仕事ができない人間」としてレッテルを貼られる前に、Sさんはいつも自ら辞めていた。
「自分に甘い」「飽きっぽい」「忍耐力がない」
そう責めながらも、「でも何かが、どうしても合わない」と感じ続けていた。
転職先でも繰り返す「最初は好調→どんどんしんどくなる」パターン
Sさんのキャリアは、転職エージェントから見れば「意欲的でフットワークが軽い人材」。
でも現実は違った。
- 新しい職場では最初はやる気満々、だけど数週間でタスクが溜まって混乱
- メールの返信に時間がかかりすぎて「何してたの?」と聞かれる
- 朝の出勤準備でバタバタして遅刻が増える
- チームのLINEに返信できずに“距離を置いてる人”と思われる
- 予定がすぐ頭から抜けて「え?聞いてなかったの?」と驚かれる
「一つ一つは小さなこと。でも、全部がボディブローみたいに効いてくるんです」
Sさんはそう振り返る。
プライベートでも“どこかズレてる”感覚
・飲み会で話のテンポについていけない
・人の話を聞いているつもりなのに、「ちゃんと聞いてた?」と言われる
・返信しないまま数日が過ぎ、気まずくて連絡できなくなる
・片づけができず、部屋は“地層のように積み重なる”状態
・時間に間に合ったことがなく、「なんでそれで許されると思ってるの?」と怒られる
「たぶん、みんなが“普通にできていること”が、私には“努力しても安定しない”んです」
28歳のある日、疲れ果てて心療内科へ
何度目かの退職後、Sさんは知人のすすめで心療内科を訪れる。
「発達障害じゃないと思うけど、一応検査してみましょう」
医師の言葉に、内心はほっとしていた。
(やっぱり違うよね。私は甘えてるだけだ)
結果は、「発達障害とまではいかないが、特性はある」=いわゆるグレーゾーンだった。
診断がつかないから、支援も届かない。でも、生きづらい
「支援制度を使えるわけでもないし、職場に言っても“で?”って反応なんですよね」
Sさんは、“何者にもなれない自分”に苦しんだ。
- ADHDじゃないと言われた
- でも普通でもない気がする
- 周りはバリバリ働いてる
- なのに私は、週5勤務すら体力的に限界
「私、どこに行っても合わないのかも」
その言葉が口癖になりかけていた頃、SさんはSNSで同じような人たちの声を目にする。
「特性を前提にした仕事選び」で変わった働き方
その中に、「発達特性のある人向けのコーチングを受けた」という投稿があった。
自分の特性や苦手を否定せず、“前提として設計する”という考え方に、彼女は衝撃を受けた。
そこから始めたことは、小さなことばかり。
- ToDoリストを「1日3つまで」に絞る
- Googleカレンダーと連動したリマインダーで予定管理
- 「連絡を後回しにしない」ルールを作る
- 同じような人と話せるコミュニティに参加する
- 短時間勤務やリモート中心の仕事に切り替える
数ヶ月後、Sさんは「働きやすい」と感じる日が増えてきた。
「私は“普通の人”にはなれない。でも、“私に合った働き方”は選べるんだ」
初めて、自分のことを受け入れられた気がした。
まとめ:グレーゾーンでも、生きづらさは「リアル」
上記エピソードは実際のインタビューで聞いたリアルな体験談です。
※掲載許可済、一部特定を避けるために描写を変えています。
Sさんのように、「診断名はつかないけど、苦しんでいる」人は少なくありません。
それは「病気じゃないから大丈夫」なのではなく、「社会の枠組みに合ってないだけ」のことも多いのです。
何者にもなれない自分を責めるのではなく、今のままの自分に合った選択肢を見つけていくこと。
それが、グレーゾーンを生きる上でのリアルで実践的な第一歩かもしれません。