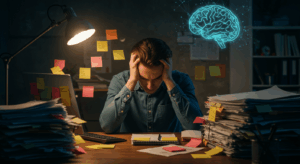「いつもギリギリ」「また遅れてしまった」
…そんなふうに自分を責めたことはありませんか?
時間にルーズなわけじゃない。
頭ではわかっていても、うまく行動に移せない。
それは、ADHD(注意欠如・多動症)特有の脳の働きが関係しているかもしれません。
本記事では、
- なぜADHDの人は時間を守るのが苦手なのか?
- ADHD脳の特徴と時間感覚の関係
- 日常で使える具体的な対策・工夫
これらをわかりやすく解説します。
なぜADHDの人は時間を守れないのか?
1. 「今」のことしか考えられなくなる
ADHDの人はタイムブラインドネス(時間盲)と呼ばれる特徴を持つことがあります。
これは、未来の予定や締め切りが「実感としてピンとこない」状態。
「あと5分で出なきゃ」とわかっていても、目の前のことに夢中になってしまい、気づいたときには時間オーバー…。
2. 脳のワーキングメモリの弱さ
ADHDの人は、一時的に情報を保持しながら行動する力(ワーキングメモリ)が弱い傾向にあります。
「準備してから出かける」という一連の段取りをすぐに忘れてしまい、気づいたら時間が足りない…ということが起こります。
3. 刺激に敏感、でも飽きやすい
興味のあることには集中しすぎて時間を忘れる「過集中」が起きやすい反面、興味のない作業は手につかない…。
その結果、準備や移動が後回しになりやすいのです。
ADHDの「時間を守れない」をラクにする5つの対策
対策①:「出発時間」ではなく「行動開始時間」を設定する
「10時に家を出る」ではなく、「9時45分に荷物を持って玄関にいる」など、具体的な行動に紐づけた時間設定が効果的です。
対策②:スマホの通知は2段階で設定する
「準備する時間」と「出発する時間」に分けて、2回アラームを鳴らすことで忘れにくくなります。
例:10時に出発なら、9:30準備開始、9:50出発通知。
対策③:「時間が見える化」されるツールを使う
- タイムタイマー(残り時間が視覚でわかる時計)
- Googleカレンダー × 通知設定
- 音声で知らせてくれるリマインダーアプリ
など、視覚・聴覚からのフィードバックを活用すると効果的です。
対策④:余裕を持って「早めの行動」を成功体験化する
「10分早く出たら余裕で着けた!」というポジティブな成功体験を記録しておくと、行動が変わりやすくなります。
小さな成功を「見える化」することで、脳が変わります。
対策⑤:コーチングや伴走型のサポートを検討する
自力で改善するのが難しいときは、ADHD専門のコーチや支援者に頼るのも有効です。
行動のクセや脳の特性に合った仕組みを一緒に作ることで、生活の質が大きく変わります。
おわりに
時間を守れないのは「だらしないから」じゃない。
それは、脳の機能と特性によ“見えにくい困りごと”です。
無理に気合や根性で乗り越えようとせず、
「仕組み」や「ツール」や「人の手」を借りて、
あなたのやり方で時間と仲良くなっていきましょう。